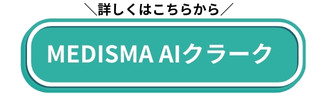AI×カルテ自動化で待ち時間を解消|クリニックの評価は「スムーズな診療体験」で変わる
- 2025年7月31日
- AI

近ごろのクリニック運営では、医師の専門性や治療の的確さだけでなく、受付の雰囲気やスタッフの対応、そして待ち時間の長さといった点も、患者さんの満足度に大きく関わっています。
とくに、診察までの待ち時間が長いと、どうしても不満を感じやすくなり、クリニック全体の印象にも影響してしまいます。
一方で、医師が一人ひとりの患者さんとしっかり向き合おうとすると、カルテの記録に時間がかかり、次の患者さんをお待たせしてしまうというジレンマがあります。
このような課題を解決する方法の一つが、AIによるカルテ記録のサポートです。
AIが記録業務を手助けすることで、医師はより安心して患者さんとの対話に集中でき、診療の質を保ちながら、スムーズな診察が可能になります。
この記事では、丁寧な診療と効率的な運営を目指し、患者満足度を向上させたいと考えているクリニックに向けて、AIが実現する新しいクリニック運営について解説します。
目次
医療の質は「結果」だけでなく「体験のプロセス」も含む
患者さんはクリニック受診する際に病気が治るという結果だけではなく、そこに至るまでの「プロセス」も、クリニックの評価として重視します。
たとえば、的確な診断が受けられたとしても、以下のような体験をした場合、患者さんの満足度は低いものになってしまうでしょう。
- 予約したのに、1時間以上待たされるのが当たり前になっていた
- 待合室が混雑しており、プライバシーや感染症への不安を感じた
- ようやく呼ばれた診察では、医師がパソコンの画面ばかり見ていて、あまり話を聞いてもらえなかった
患者さんがクリニックに安心感や信頼感を抱くのは、治療の結果だけではありません。
待ち時間が短く、医師が親身になって話を聞いてくれるといった、積み重ねによって、それらは生まれます。
つまり、患者さんは「待ち時間の少なさ」と「質の高い丁寧な診察」によってクリニックに満足するのです。
待ち時間の根源は「丁寧な診療」と「記録業務」のジレンマ
多くのクリニックが抱える待ち時間の問題は、「丁寧な診療」と「カルテ記録業務」という、どちらも欠かせない業務の板挟みになることから生じています。
厚生労働省「令和5年受療行動調査」によると、医療機関の診察時間は、以下のようになっています。
- 10分~20分未満:15.0%
- 5分~10分未満:40.9%
- 5分未満:28.1%
質の高い診療のためには、患者さんから詳しく話を聞き、それに基づいて丁寧に説明することが欠かせません。
しかし、診療内容を後から正確にカルテへ記録するには、まとまった時間と集中力が必要です。
一般的に、医師は一人の患者さんの診察を終えた後、あるいは診察の最中にカルテに記載します。
仮に1人の患者さんの記載に5分かかるとすると、患者さんが12人いれば約1時間かかります。
カルテに記載する際は、診察内容を整理しながらキーボードで入力する必要があるため、誤入力などに注意しなければいけません。
診察時に医師が電子カルテの画面に向かう時間が長引けば、その分、患者さんと向き合う時間は短くなります。
医師が丁寧な診療をしたいと願っていても、時間に追われることで結果的に医療の質が低下し、待ち時間も解消されないという状況になります。
「聴く」こと「記録する」ことを分けた新しい診療スタイル

カルテ記録の負担軽減を期待できるのが、AI技術を活用した「AIクラーク」というシステムです。
医師と患者さんの診察中の会話をAIがリアルタイムで認識し、自動でテキスト化します。
さらに、テキスト化された内容を以下のようなSOAP形式に沿って整理し、電子カルテに反映させます。
- S(主観的情報):患者さんの訴えや症状
- O(客観的情報):検査結果やバイタルサインなどの数値
- A(評価):医師による診断の見立てや考察
- P(計画):治療方針や次回受診の指示
これにより、従来は診察と同時ににおこなっていたカルテ記載の大部分が、入力することなく自動的に進めることが可能です。
もちろん、AIによる記録が完璧というわけではありません。
最終的な確認や微調整は医師がおこなう必要があります。
しかし、作業は「ゼロから情報を入力すること」から「AIが作成した下書きを確認・承認する」ことへと変化します。
この変化によりカルテ業務の負担が軽減されるため、医師は残業時間の短縮やワークライフバランスの改善ができるでしょう。
記録業務の効率化が実現する「診察回転率」の向上
カルテ記録業務の効率化は、そのまま診療全体の効率化、すなわち「診察回転率の向上」に直結します。
たとえば、これまで5分かかっていたカルテ記録が、AIクラークの活用によって1〜2分に短縮されたとします。
患者さん1人あたり3〜4分の余裕が生まれ、その分患者さんの診療に充てたり、別の業務をおこなったりすることが可能です。
結果として、1時間あたりに診療できる患者数も自然と増加し、クリニック全体の生産性が向上するでしょう。
特に、予約制で運営しているクリニックにとって大きなメリットです。
たとえば、急患の対応や、想定より診察に時間がかかった患者さんがいても、全体のスケジュールが乱れにくくなります。
診察時間が短縮されることで、予約患者さんへの影響を最小限に抑えられ、「待ち時間の少ないクリニック」としての信頼を築く一歩となります。
待ち時間が減少することで、患者さんの間で「あのクリニックは予約時間通りに診てくれる」という評判が広がり、患者さんが継続して通院しやすくなるでしょう。
「プロセスの質向上」は患者さん満足度に直結する
AIクラークの導入がもたらすのは、時間的な効率化だけではありません。
むしろ、診療という「プロセスの質」を向上させ、患者満足度を高める点にあります。
医師がカルテ入力の負担から解放され、患者さんの顔を見て、じっくりと話を聞くことに集中できるようになります。
これは、患者さんにとって「自分の話を聞いてもらえた」「親身になってくれている」と感じられ、安心感と信頼感につながることがメリットです。
その上、診察から会計までの流れはスムーズで、短い待ち時間で会計まで完了できます。
このような「よく話を聞いてくれるのに、待ち時間が少ない」という診察により、満足した患者さんによる口コミを通じて広がり、クリニックの評判を高めることが可能です。
また、良い循環はスタッフの業務負担にも関わってきます。
診察がスムーズに進むことで、患者さんからの待ち時間に関する問い合わせ対応が減り、受付業務の混乱が解消されます。
スタッフは本来の業務に集中でき、患者さん一人ひとりに対してより丁寧な対応ができるため、クリニック全体のサービス向上にも貢献するでしょう。
メディスマAIクラークが実現する“流れの良い診療”とは
「メディスマAIクラーク」は、患者さんと話すだけで記録ができるという新しい診察を実現できるシステムです
。医師が患者さんとの対話に集中している間に、その内容が自動でカルテに記録されていくため、医療の質を損なわずに診察のスピードを上げられます。
このシステムを利用することで、医師は記録業務から解放されて診療に集中でき、患者さんは待ち時間が短縮され、スタッフは円滑なクリニック運営に貢献できます。
つまり、関わる人すべてにとって、より効率的な時間の使い方が可能です。
- 医師:記録業務が軽減され、患者さんとの対話に集中できる
- 患者さん:待ち時間が短縮され、かつ丁寧な診察を受けられることで、満足度が向上する
- スタッフ:業務が円滑に進むことで負担が軽減され、より質の高い患者対応が可能になる
「メディスマAIクラーク」は、、患者さんの待ち時間を短縮しながら、医療の質を高める診療環境の構築を力強くサポートします。
「待たせないクリニック」は、準備されたクリニック

これまで、多くの医療現場では「質の高い医療のためには、時間がかかるのは仕方ない」という一種の共通認識がありました。
しかし、テクノロジー、特にAIの進化は、その前提を大きく変えようとしています。
AIによるカルテ記録支援システムは、キーボード入力を代替するツールではありません。
診療時間や待ち時間を含めたクリニック全体の「時間の使い方」そのものを最適化し、「質とスピードの両立」という新しい診療スタイルを確立するための、有効な戦略的投資と言えます。
「時間がかかるのは仕方ない」という諦めから、「テクノロジーで時間を創造する」という発想へ。
未来を見据えた準備と、テクノロジー活用の決断が、これからのクリニック経営の明暗を分けるでしょう。
「メディスマAIクラーク」の導入により、患者さんから選ばれ、スタッフが働きやすく、経営的にも安定するため「待たせないクリニック」を実現できるはずです。
ぜひご検討ください。
<参考サイト・文献>
令和5年受療行動調査|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jyuryo/23/dl/kakuteisu-kekka2023.pdf