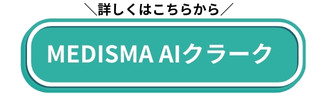AI×音声入力で診療をもっと安全・丁寧に|医療の質は「記録のしかた」で変わる
- 2025年7月30日
- AI

「医療の質」と聞くと、治療の成果や検査データをイメージしやすいですが、実はその過程も同じくらい大切なものと考えられます。
医師の問診や観察、判断、そして記録といった一つひとつが、安心と信頼につながる医療の土台です。
しかし実際の医療現場では医師は、診察中に「聴く」「話す」「記録する」を同時にこなさなければならないことも多く、負担がかかりミスにつながる可能性があります。
そこで注目されているのが、音声入力とAIによるカルテ記録の支援です。
診療の質を落とさず、医師が病状を把握したり、患者さんの訴えを聞いたりすることに集中できる環境をつくり出します。
医療の質を高めて、患者満足度を向上させたいと考えている先生方はぜひ参考にしてください。
目次
医療の質とは「結果」とともに「過程」も含む
患者さんがクリニックを選ぶ基準の一つは、医療の質の良さです。
医療の質が良いとされるクリニックとはどのような特徴があるのでしょう。
医療の質を支えるプロセス
医療は「治癒したかどうか」という結果だけで評価されがちですが、問診で話を丁寧に聞いてくれたか、対応は親身であったかなどの過程も患者さんにとっては重要です。
例えば、的確な診断や治療ができる医師だとしても、以下のようなケースが生じている場合、患者さんの満足度は低い傾向があります。
- 受付の対応が悪い
- 看護師のケアが雑で怖い
- 医師が高圧的で話しにくい
つまり、患者さんにとっての安心感や信頼感を醸成することが、医療の質を高め、医療安全の確保につながります。
記録は評価指標と診療報酬の根拠になる
診療情報の記録指針2021でも「診療情報の適切な記録と管理は、安全・安心な医療の提供を実現するために必須である」と明記されており、記録の重要性は明確に位置づけられています。
また、政府が進める「医療DX(デジタル・トランスフォーメーション)(*)」の流れのなかでも、診療記録の電子化・標準化は取り組みの中心です。
より正確なデータの整備は、医療の質の向上、医療安全といった多方面に影響を及ぼします。
さらにカルテの記載は単なる記録にとどまらず、診療報酬の算定に欠かせないものです。
医療制度でも重要な役割を担い、以下のような様々なシチュエーションで役立ちます。
- インフォームドコンセントの記録:患者さんの自己決定権を尊重し、医療者と患者さんの間で十分な情報共有が行われたことを示す法的・倫理的な根拠となる
- 薬剤処方と服薬指導の記録:患者さんが適切に薬剤を使用するための情報提供が行われたことを示し、副作用が発生した場合の原因究明や判断材料にもなる
- 検査結果とその評価の記録:疾患の診断、治療効果の判定、病状の変化の把握に不可欠な情報となる
診察中、医師は患者さんの話を聴き、診断方針を判断しながら、リアルタイムでこれらの内容をカルテに入力することが必要です。
この同時進行の作業は、集中力の低下やミスを生みやすく、医療の質の低下にもつながる恐れがあります。
ここで注目したいのが、AIによるカルテ記録と音声入力技術によるサポートです。
会話をして入力する診療から、聴くだけの記録のスタイルへ移行することで、診療の過程の記載を自動化できるため、医師の負担を軽減して、医療の質を高めることが期待できます。
(*)医療DX(デジタル・トランスフォーメーション):医療の現場にデジタル技術を取り入れて、診療・業務・経営の質を向上させる取り組みのこと
「聴く」ことと「記録する」ことを分けた診療スタイル
医師の診察では、以下のような作業が伴います。
- 患者さんの話を聞く
- カルテに入力する
- 診療方針や治療方針を決定する
こうした環境では、医師は複数の作業を並行して行うこととなり、集中力が分散してしまい、本来の適切な医療提供を十分にできないというケースを招いてしまうこともあります。
これは、患者対応の質や医療の質を低下させてしまう要因となります。
医師の本来の重要な役割である「聴くこと」に集中するためには、聴くことと記録することを分ける工夫が必要です。
そこで有効なのがカルテの入力作業において音声入力やAIを活用するということです。
この実現により、医師は対話に専念でき、患者さんの悩みや不安な気持ちに寄り添えるようになります。
この役割分担の考え方が、ひいてはヒューマンエラーを防止し、医療の安全性と質の向上につながるでしょう。
音声入力×AIが実現する「より詳細な観察」

音声入力とAIによる記録支援の強みは、医師が診察に集中できる環境をつくる点です。
カルテ入力に気を取られず、患者さんの表情や仕草、声のトーンといった微細な変化にも目を向けられるようになります。
これらの情報は、患者さんの病状を把握して、正確な診断をするうえで重要です。
カルテの記載にはさまざまな形式がありますが、多くの医療機関で用いられているのがSOAP形式です。
- S(主観的情報):患者さんの訴えや症状
- O(客観的情報):検査結果やバイタルサインなどの数値
- A(評価):医師による診断の見立てや考察
- P(計画):治療方針や次回受診の指示など
SOAP形式は、情報を簡潔にまとめられるため、スタッフ間でも情報共有しやすいのがポイントです。
音声入力で記録された診療内容は、AIにより自動でこの形式に整理され、リアルタイムにカルテに反映されます。
そのため、入力する手間が省けるだけではなく、診察後すぐに内容を振り返ったり、ほかの医師やスタッフと情報共有したりする際にも活用しやすくなります。
こうして記録の正確性と活用性が高まることで、より的確で患者さんに寄り添った医療の提供が可能になります。
医師が判断に集中できる環境が整えば、診療がより丁寧になり、結果として医療の質そのものが高まるでしょう。
医療記録の精度と再利用性が変わる
医療記録を音声で記録することで、患者さんの言葉をそのままカルテに残せるようになります。
たとえば「ズキズキ痛む」「どんどん悪化している」といった感覚的な表現も正確に記録できるため、より良い診療につながります。
AIが自動でSOAP形式に情報を整理してくれるので、あとから見返したり、ほかの医療スタッフと共有したりするのも簡単です。
情報がきちんとまとまっていると、急な対応が必要なときにもすぐに確認できて安心です。
また、手書きや手入力でありがちな「書き間違い」や「記入漏れ」などのヒューマンエラーも減らせます。
例えば、薬の量や回数などを入力する際に「2mg」を「20mg」と間違える、患者さんのアレルギー情報の記載が漏れるなどのミスを事前に防げます。
このように、音声入力とAIを使えば、医療的な指示がしっかり残るため医療の安全性も高まり、チームでも使いやすい記録となります。
さらに、患者さんとのやりとりを丁寧に記録することは、信頼関係を築くうえで重要です。
記録の質と対話記録の質は、それぞれ医療の安全と信頼を支える柱といえます。
どちらも、信頼される医療には欠かせない要素です。
「プロセスの質向上」は患者満足度に直結する
医師がしっかり話を聞いて、丁寧な対話を心がけるという姿勢は、患者さんに安心感を与え、信頼感が高まります。
治療の効果だけでなく、「よく話を聞いてもらえた」という実感が、患者満足度の向上につながるでしょう。
さらに、正確な記録で整理されていれば、治療内容や注意点を患者さんと一緒に振り返ることができるため理解も深まります。
こうした「一緒に治療に取り組んでいる」という感覚は、医師と患者さんが信頼関係を築くうえで重要です。
患者さんは「わかってもらえた」「大切にされている」と感じられる診療が、医療の質そのものを高めていきます。
メディスマAIクラークが実現する“質の高い診療”とは
「メディスマAIクラーク」は、医師と患者さんの音声をリアルタイムで解析し、SOAP形式でカルテを自動に作成するAI音声入力システムです。
診療の流れを止めることなく「記録」と「対話」の両立を実現します。
導入したクリニックでは、「自分で入力するよりも効率的にカルテの記入ができるようになった」「単調な表現ではなく、患者さんとの会話も具体的な言い回しを意識するようになった」といった声も上がっています。
特に、心療内科や精神科といった対話が中心の診療科、ほかにも対話を大切にしている医師にとって、電子カルテへの入力は負担が大きいものでした。
しかし、メディスマAIクラークにより、対話の内容が要約され記録されることで、患者さんとの対話に集中できるようになります。
また、記録の精度が向上することで、カンファレンスや多職種連携の質も高まり、チームで正確で詳しい情報が共有され、患者さんの一貫したケアにもつながります。
近年はSOAP形式による記録が制度的にも重視されており、正確で整理されたカルテは診療報酬の算定や院内監査でも役立ちます。
医療機関としての信頼性や透明性の向上にもつながるツールと言えるでしょう。
医療の質は、まず“記録のあり方”から変えられる

医療の質は、治療結果だけでなく、その過程をいかに丁寧に積み重ねたかによっても左右されます。
問診、観察、判断、記録といった一連の診療プロセスが、患者さんの安心と信頼のもととなり、患者満足度の向上につながるといえます。
近年、電子カルテの入力にAI音声入力を導入することで効率化を図り、医師が本来の診療に集中できる環境を作ろうという気運が高まっています。
「メディスマAIクラーク」は、こうした診療体制の実現を支援する有効な手段のひとつです。記録精度の向上と業務効率化の両立を目指す医療機関にとって、導入を検討する価値のあるツールといえるでしょう。
<参考サイト・文献>
診療情報の記録指針2021|診療情報管理学会
https://jhim-e.com/pdf/data2021/recording_guide2021.pdf