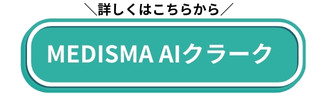電子カルテの使い方|医療事務への教え方と入力負担を減らす秘訣

電子カルテを導入したけれど、「操作が難しくて、かえって時間がかかる」といった医療事務スタッフの声が挙がることがあります。高額な費用をかけて導入したにもかかわらず、現場で十分に活用されなければ、業務の非効率化を招きかねません。
医療事務スタッフの電子カルテへの抵抗をなくすためには、使い方を丁寧に教えることが大切です。
本記事では、医療事務スタッフへ電子カルテ教育を成功させるための具体的な手順を詳しく解説します。さらに、教育だけでは解決しきれない入力業務の負担を減らす秘訣も紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
医療事務に電子カルテの使い方を教える3ステップ

電子カルテの教育を成功させるには、計画的な準備が不可欠です。受付・会計・レセプト業務を例に挙げ、医療事務スタッフに電子カルテの使い方を教えるための具体的な3つのステップを解説します。
- ステップ①:院内マニュアルを作成する
- ステップ②:研修計画を立てる
- ステップ③:実践ノハウで定着させる
ステップ①:院内マニュアルを作成する
電子カルテのベンダーが提供するマニュアルは、機能の「辞書」であっても、日々の業務の「教科書」にはなりません。スタッフが本当に必要としているのは、次に何をすべきかが視覚的にわかる実践的なガイドです。
現場で使われるマニュアルは、以下の5つの要素で構成しましょう。
|
マニュアルの構成要素 |
|
①基本操作 |
|
ログイン方法や患者検索など、全ての業務の基礎となる操作をまとめます。 |
|
②業務フロー別操作 |
|
マニュアルの核となる部分です。「新患受付」「会計」など具体的なシーン別に、手順をスクリーンショット付きで解説します。 |
|
③イレギュラー対応集 |
|
「保険証が月の途中で変わった」など、頻度は低いものの迷いやすいケースの対応方法を記載します。 |
|
④よくある質問(FAQ) |
|
「領収書を再発行したい」など、業務で患者から寄せられる質問と回答を記載します。 |
|
⑤トラブルシューティング |
|
「画面が固まった」などのトラブルに対する初期対応フローを掲載します。 |
マニュアルはスクリーンショットを活用し、視覚的にわかりやすい構成にしておくことが重要です。また、共有フォルダなどでデジタル管理し、常に最新の状態を保つルールを設けましょう。
ステップ②:研修計画を立てる
研修は一度きりではなく、導入前から導入後にかけて継続的に行うことで効果を高められます。特に、短時間の研修を複数回実施する方が記憶に定着しやすいでしょう。
効果的な研修の鍵は、集合研修とOJT(On-the-Job Training)の効果的な組み合わせです。
- 集合研修:全員が同じ基礎知識を共有するため、システムの全体像や基本操作、個人情報保護などのルール説明を行います。時間は60分〜90分程度に留め、実際に操作する時間を設けましょう。
- OJT(On-the-Job Training):集合研修で学んだ知識を、実際の業務の中で先輩スタッフの指導のもと実践することで、スキルとして定着させます。指導者は業務手順だけでなく、「なぜその業務が必要か」を細かく説明することが大切です。
また、院内での教育を補完するために、外部のリソースを活用するのも有効です。例えば、以下のような講座や問題集、Webサービスを活用してみましょう。
- 日本医療事務協会「医療事務コンピュータ・電子カルテ講座」
- 医学通信社「初級者のための医療事務【BASIC】問題集」
- 無料タイピング練習サービス「e-typing・医療介護」
▼関連記事
電子カルテ入力は難しくない!練習ツールや代行入力、音声入力AIを紹介
ステップ③:実践ノウハウを定着させる
研修で学んだ知識を「使えるスキル」へと昇華させるには、日々の業務での実践と成功体験の積み重ねが不可欠です。スタッフ一人ひとりの習熟度に合わせた目標設定と、学びを促進する仕組みづくりが重要となります。
例えば、朝礼などで「セット機能を使ったら入力が早くなった」といった小さな成功体験を共有し合うことで、他のスタッフのモチベーション向上にもつながるでしょう。
具体的な実践ノウハウに関しては、次の章で解説します。
【すぐに教えられる】電子カルテの使い方実践ノウハウ集

医療事務スタッフが業務で直面しやすい問題を解決するための、即効性の高いノウハウを紹介します。マニュアルづくりや教育に役立ててみてください。
- よくある入力ミスと防止策5選
- 便利機能とテンプレート活用でスピードUP
- パニックにならない!トラブル対応フロー
1. よくある入力ミスと防止策5選
日々の業務で発生しがちな入力ミスは、レセプト返戻や患者トラブルの主な原因です。代表的な5つのミスについて、原因と対策は以下のとおりです。
|
よくある入力ミス |
原因 |
対策 |
|
保険証情報の入力ミス |
目視による確認への過信や、確認作業の形骸化 |
・オンライン資格確認を毎回の必須業務としてルール化する。 ・月初にはスタッフが指差し、声出しで券面と画面を確認する。 |
|
「病名漏れ」によるレセプト返戻 |
医師のカルテ記載から請求に必要な正式傷病名をスタッフが判断できていない、または入力忘れ |
・「この検査をしたらこの傷病名が必須」という院内ルールの一覧表を作成、掲示する。 ・電子カルテの病名チェック機能を必ずONにする。 |
|
摘要欄の記載不備 |
特定の管理料算定時に必要な定型コメントの知識不足 |
・指摘が多い項目の正しいコメントを電子カルテの「テンプレート機能」に登録し、ワンクリックで入力できるようにする。 |
|
別患者のカルテへの誤入力 |
複数のカルテを同時に開いたままの作業や、本人確認の省略 |
・入力直前に画面上の「フルネーム」と「生年月日」を声に出して確認するルールを徹底する。 ・可能であれば患者の顔写真を登録する。 |
|
薬剤の用量・単位の間違い |
医師の手書き指示の判読ミスや、単純なタイプミス |
・医師に直接オーダーを入力してもらう体制を推進する。 ・頻用薬を標準的な用量とともに「セット」として登録し、手入力の機会を減らす。 |
▼関連記事
電子カルテの入力ミスを訂正するには?正しい修正方法と減らす対策
2. 便利機能とテンプレート活用でスピードUP
操作に慣れたら、次は入力スピードが求められます。特に「テンプレート(セット登録)機能」は、入力業務の多くを自動化できる機能です。単なる処方だけでなく、「所見・処置・検査・処方・傷病名」を一つのパッケージとして登録できます。
|
テンプレートの活用例 |
|
①初診セット |
|
初診料や「主訴:」「現病歴:」などの見出しのみの所見テンプレートを登録します。 |
|
②感冒セット |
|
「急性上気道炎」の傷病名、典型的な処方、定型的な所見を登録します。症状に応じて微調整するだけでカルテ入力が完了します。 |
|
③特定健診セット |
|
必須の血液検査項目や「特定健康診査の疑い」の傷病名を一括登録します。煩雑な検査項目のオーダーミスを防ぎます。 |
また、自院の電子カルテで使えるショートカットキーを一覧にしてPCの横に貼っておくことも、スピードアップに有効です。
3. パニックにならない!トラブル対応フロー
医療事務の業務で起こりがちな電子カルテ特有のトラブルに対し、シンプルな確認手順を院内に掲示しておくことで、スタッフが冷静に対応できます。以下のようにトラブル例を整理し、共有しましょう。
トラブル例①:いつもと表示が違う・表示がおかしい
- 画面に表示されている氏名・生年月日が対象患者と一致しているか指差し確認する。
- 患者が正しい場合、自分のアカウントでログインしているか確認する(表示レイアウトはユーザーごとに設定が異なる場合があるため)。
- 解決しない場合、PCを再起動する。
- 再起動しても解決しない場合はベンダーへ報告する。
トラブル例②:オンライン資格確認ができない
- カードリーダーとPCの接続ケーブルが抜けていないか確認する。
- インターネット接続に問題がないか、他のWebサイトが開けるかなどで確認する。
- カードリーダーの電源を切り、入れ直してみる。
- 解決しない場合、担当者やベンダーのサポートデスクへ連絡する。
医療事務に電子カルテの使い方を教える3つのポイント

電子カルテの教育を成功させるためには、スタッフの不安や疑問に寄り添い、クリニック全体で取り組む姿勢を示すことが重要です。教育を進める上で特に押さえておくべき3つのポイントを解説します。
- 電子カルテの導入目的を伝える
- 反対意見を受け止める
- 紙カルテの併用は期限を決める
1.電子カルテの導入目的を伝える
院長が導入後の教育を現場スタッフやベンダーに丸投げせず、主体的に関わることが重要です。「どの業務をどう改善したいのか」という具体的な目的を院長自ら伝え、自院独自のフローを盛り込んだマニュアルを策定しましょう。
2.反対意見を受け止める
「今までのやり方がよかった」など、スタッフから挙がる反対意見はしっかり受け止めましょう。現場の意見に耳を傾ける姿勢が、スタッフの不満を解消し信頼関係を築きます。
反対意見があれば、まずは理由を聞きましょう。「操作を覚えられない」「結局紙カルテと併用していて業務が増えた」などの悩みが明らかになります。悩みを受け止めた上で、改善点を一緒に検討していくことが大切です。
3.紙カルテの併用は期限を決める
「慣れるまで」という理由で期限を決めずに続けると、二重管理によってかえって効率が悪くなります。スムーズな移行を促すため、あらかじめ紙カルテを完全にやめる期限を設定し、院内全体で共有しましょう。
教育だけでは解決しない?医療事務の負担を生む根本原因

電子カルテの操作教育は重要ですが、それだけでは解決できない問題があります。実は、医療事務の業務負担の多くは、「手入力のデメリット」や「医師のカルテ業務」に起因しているケースが少なくありません。
教えるだけでは超えられない「手入力のデメリット」
スタッフのスキルが向上したとしても、手入力から生じる根本的な課題は残ります。例えば、入力時間や入力ミス、業務の属人化が挙げられます。
- 入力時間:タイピング速度には個人差があり、教育コストをかけても限界がある
- 入力ミス:レセプト返戻や医療過誤に直結する
- 業務の属人化:スキルの高いスタッフが不在の日に業務が滞ってしまう
負担の根源は「医師のカルテ入力」にある
医師のカルテ入力が遅れれば、会計待ちの患者対応は医療事務の仕事です。医師のカルテに病名漏れや記載不備があれば、レセプト返戻につながり、その再請求作業も医療事務が担います。
つまり、医師の入力業務が医療事務の残業やストレスの原因となっているのです。
医師の入力負担軽減に「医療クラーク」は活用できる?
医師の入力負担を軽減する手段として、医療クラーク(医師事務作業補助者)の配置が考えられます。医療クラークは、医師の指示のもとでカルテの代行入力などを行う職種です。
しかし、クリニックでの運用には現実的な課題も存在します。採用後の育成に時間とコストがかかり、スタッフによってスキルのばらつきも生じやすいでしょう。
さらに、医療クラークの配置による診療報酬上の「医師事務作業補助体制加算」は、急性期医療を担う病院が主な対象であり、多くのクリニックでは算定が難しいのが実情です。
▼関連記事
医療クラーク(メディカルクラーク)とは?医療事務との違いや電子カルテ入力など業務を解説
医師のカルテ入力を自動化するにはAI音声クラークがおすすめ
医師のカルテ入力を効率化することで、結果的に医療事務全体の業務負担軽減につながります。医療クラークの採用が難しい場合、AI音声クラークによる入力作業の自動化が効果的な解決策となります。
AI音声クラークは、診察中の医師と患者の会話を録音し、電子カルテ上へSOAP形式でまとめるツールです。誤認識しやすい医療用語や自院独自の言葉もAIが学習し、正しく出力可能です。
▼関連記事
電子カルテの音声入力は役に立つ?AI活用の効果と導入のポイント
株式会社HERO innovationでは、病院やクリニックで活用いただける電子カルテAI音声入力システム「MEDISMA AIクラーク」をご提供しています。もし入力業務の負担軽減や教育コストでお悩みなら、ぜひ一度お問い合わせください。
電子カルテの有効活用で医療事務の業務改善を

電子カルテの使い方を医療事務に教えるには、実践的なマニュアルで自院の業務に沿った手順を伝えることが大切です。そして、教育の前には導入目的を明確に伝え、スタッフの反対意見も受け止めましょう。紙カルテとの併用には必ず期限を設けることがポイントです。
しかし、スタッフが感じる困難の根本原因は、手入力の限界や医師の入力業務に起因することも少なくありません。教育と並行し、医療クラークやAIクラークの活用で入力業務そのものを見直すことが、真の負担軽減につながるでしょう。