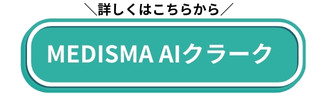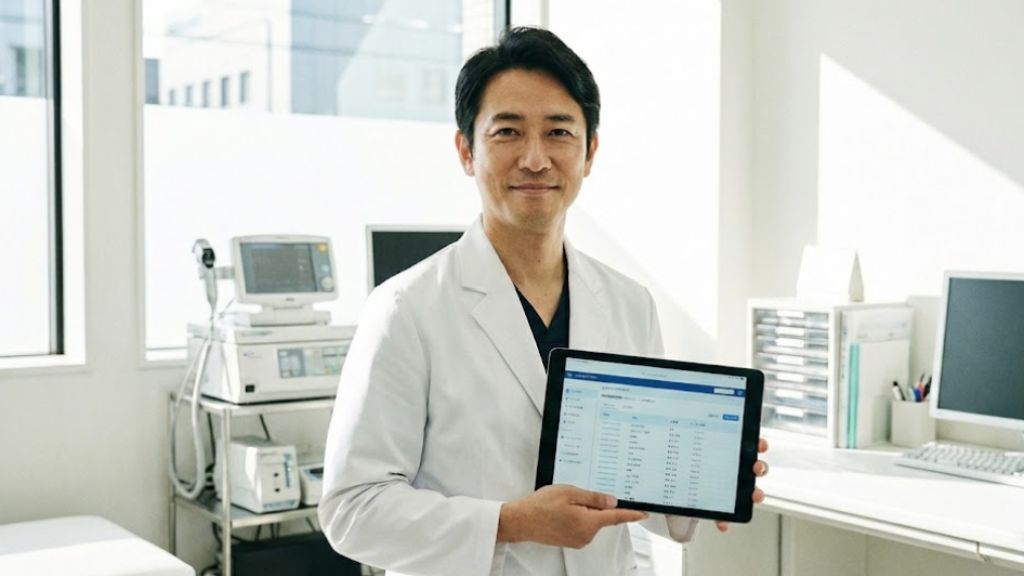【開業医向け】医師の働き方改革がもたらすクリニックへの影響と対策

「医師の働き方改革で、大学病院から紹介される非常勤医師の確保が難しくなった」「医師数が減って自分の負担が増えた」と感じていませんか。
2024年4月施行の「医師の働き方改革」の新制度は、勤務医の労働時間に上限を設けるものです。一方で、「対象外」とされる開業医にも影響をもたらしています。
本記事では、医師の働き方改革が開業医に及ぼす具体的な影響と、クリニックが安定して成長していくための実践的な対策を解説します。この記事を読むことで、院長の業務負担増加の背景を理解し、クリニックの運営体制を見直すためのヒントとなれば幸いです。
目次
開業医にも影響する「医師の働き方改革」とは?

医師の働き方改革は、長時間労働が常態化していた勤務医の健康を守り、持続可能な医療提供体制の確保を目的として2024年4月より施行されました。原則として、医療機関に雇用される勤務医の時間外・休日労働は、適用される水準に応じて制限されます。
具体的には、以下のように「A水準」「B水準」「C水準」が設定されています。

引用:医師の働き方改革〜患者さんと医師の未来のために│厚生労働省
勤務医に原則的に適用されるのはA水準であり、時間外・休日労働を年間960時間以内にすることが義務付けられています。開業医自身は、直接的な規制対象ではありません。
ただし、クリニックで非常勤として勤務する医師は、複数の医療機関で勤務するための「連携B水準」が適用される場合があります。「連携B水準」が適用される勤務医は、時間外労働の上限(年間1,860時間)に、副業・兼業先であるクリニックでの労働時間も「通算」しなければなりません。
「労働時間の通算義務」により、勤務医を派遣する大学病院などは、所属医師の労働時間を管理する必要が生じています。結果として、管理が難しい外部での労働、つまりクリニックでの非常勤勤務を制限する動きにつながっています。
開業医は規制の対象外であっても、非常勤医師の確保が難しくなるという形で経営上の影響があるのです。
参考:医師の働き方改革│厚生労働省
医師の働き方改革で開業医が受ける3つの影響

医師の働き方改革により、クリニック・開業医が受ける影響は以下の3つです。
- 非常勤医師の採用難
- 地域の基幹病院の受け入れ縮小
- 勤務医の開業増加
1. 非常勤医師の採用難
クリニックへの直接的な影響の一つは、非常勤医師の確保が難しくなることです。多くのクリニックが専門外来や院長の休暇代替などを非常勤医師に頼っているケースも少なくありません。
しかし、働き方改革により、大学病院などは時間外労働の上限を守るため、 医師のアルバイトを制限する動きがあります。
実際に、厚生労働省の調査(令和6年12月6日時点)では、働き方改革に関連して大学・他医療機関から「医師の引き揚げがあった」と回答した医療機関は5.3%でした。少ない割合ではあるものの、非常勤医師の減少は一定数生じているといえます。
クリニックは非常勤医師を確保しにくくなり、院長自身の業務負担が増大するケースが考えられます。
参考:令和6年度医師の働き方改革の施行後状況調査 調査結果│厚生労働省
2. 地域の基幹病院の受け入れ縮小
中長期的に影響を及ぼすのが、地域医療連携体制の変化です。基幹病院も労働時間規制に対応するため、救急医療体制や外来診療体制を縮小する動きが進んでいます。
「2025年度医師の働き方改革に関する状況調査」では、医療体制への影響が生じている病院は11.6%に上りました。そのうち、具体的な影響の上位3つは以下のとおりです。
- 宿日直体制の維持が困難:71.0%
- 外来診療体制の縮小・撤退:37.4%
- 救急医療の縮小・撤退:35.3%
地域の医療提供体制において、外来診療や救急医療の提供が減少しつつある現状がうかがえます。そのため、開業医にとっては2つの問題が生じる可能性があります。
- 紹介患者の受け入れ停止:これまで基幹病院に紹介していた重症患者や専門外の患者の受け入れを断られるケースが増える。
- 基幹病院からの患者紹介の増加:基幹病院が外来診療を縮小する代わりに、軽症患者や慢性期の患者を地域のクリニックへ紹介する流れが増える。
結果として、クリニックは自院で対応しなければならない患者が増えるおそれがあるでしょう。
参考:2025年度医師の働き方改革に関する状況調査│公益社団法人全日本病院協会
3. 勤務医の開業増加
働き方改革による労働時間の制限は、勤務医の収入減につながります。そのため、勤務医が労働時間規制の対象外である「開業」を選ぶ動きが増えるでしょう。実際に、近年では病院数は減少する一方で、無床診療所の数は増加傾向にあります。
新規開業医、特に大学病院などでITツールに慣れ親しんだ医師は、開業当初からWeb予約やWeb問診などを導入し、業務効率と患者利便性を追求します。既存の開業医にとっては、ITを駆使したクリニックとの競争が厳しくなる状況も考えられます。
参考:令和6(2024)年医療施設(動態)調査・病院報告の概況│厚生労働省
開業医ができる「医師の働き方改革」への対策

医師の働き方改革による開業医への影響をどのように備え、対応すればよいのでしょうか。大切なのは、院長個人の努力に頼る運営から、タスクシェアやITツールによる運営体制への転換です。具体的な対策を3つ紹介します。
- 活用できる助成金・補助金を申請する
- タスクシフトで業務を分散する
- 医療DXで業務を効率化する
1. 活用できる助成金・補助金を申請する
業務効率化のための設備投資やシステム導入が、多くのクリニックで検討されています。国もその重要性を認識しており、導入を支援する制度を整備しています。具体的には以下の2つです。
- 働き方改革推進支援助成金:厚生労働省が管轄し、労働時間の短縮や業務効率化に資する設備・機器の導入を支援します。成果目標の達成が必要ですが、助成上限額や助成率が高い場合があります。
- IT導入補助金:経済産業省が管轄し、中小企業(医療法人を含む)のITツール導入を支援します。
必要なツールを導入する際に助成金・補助金を活用することで、投資コストを抑えることが可能です。
参考:働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)│厚生労働省
参考:IT導入補助金│IT導入補助金2025
2. タスクシフトで業務を分散する
院長の業務負担を軽減するには、他のスタッフでも可能な業務を積極的に振り分ける「タスク・シフト」が有効です。
特に効果が期待されるのが、「医師事務作業補助者(医療クラーク)」の活用です。医師の指示のもと、カルテ入力代行、診断書や紹介状の下書きなどを任せることで、医師の業務負担軽減につながります。
厚生労働省の調査では、医療クラークを採用した医療施設のうち42.6%が、外来への配置が効果的であったと回答しています。医師の増員(32.9%)を上回る効果が示されており、人手不足解消の方法として効果的です。
参考:令和2年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査(令和2年度調査)の 報告案について│厚生労働省
医療クラークに任せられる業務内容や具体的な効果については、関連記事もご覧ください。
▼関連記事
医療クラーク(メディカルクラーク)とは?医療事務との違いや電子カルテ入力など業務を解説
3. 医療DXで業務を効率化する
増え続ける業務負担に対応するには、医療DX(デジタルトランスフォーメーション)による業務効率化も選択肢の一つです。
例えば、Web問診や予約システムは受付業務を、自動精算機は会計業務の負担を軽減します。これらの業務効率化と並行し、特に院長の負担となりやすい「カルテ入力」の自動化も検討することが求められます。
なぜなら、働き方改革の影響で非常勤医師が減り、院長一人の診察数が増加すれば、カルテ入力の負担が業務全体のボトルネックとなりかねないためです。
解決策は「AI音声入力システム」
カルテ入力の課題に対しては、AI音声入力システムの活用が有効です。AI音声入力システムは、診察中の医師と患者の会話をAIが自動で認識し、SOAP形式のカルテ下書きを作成するものです。
医師は患者との対話に集中でき、診察後のカルテ入力作業の大幅な軽減につながります。また、診察終了とともにカルテの大部分が完成するため、電子カルテの事後入力も必要なくなります。
働き方改革による人手不足の影響を受ける場合、まずは電子カルテの入力負担を軽減することから始めてみてはいかがでしょうか。
▼関連記事
電子カルテの音声入力は役に立つ?AI活用の効果と導入のポイント
人材やDXツールへのタスクシフトを進めましょう

2024年から始まった医師の働き方改革は、開業医にとっても関係するものです。非常勤医師の確保難や地域の医療提供体制の変化により、院長の業務負担は増加する可能性があります。
院長一人の頑張りに頼るのではなく、スタッフへのタスクシフトを進めるとともに、医療DXを積極的に活用して業務を効率化することが求められます。
特に負担の大きいカルテ入力の自動化は、クリニックの生産性を高める上で効果的です。
ヒーローイノベーションでは、クリニックで活用いただける「MEDISMA AIクラーク」を提供しています。AIによる自動入力はもちろん、QRコード連携やタブレットでの使用も可能で、状況に応じて導入しやすい点が特徴です。お気軽にご相談ください。