【診療科別】事前問診を導入する効果は?Web問診のメリットを解説
- 2025年7月10日
- Web問診
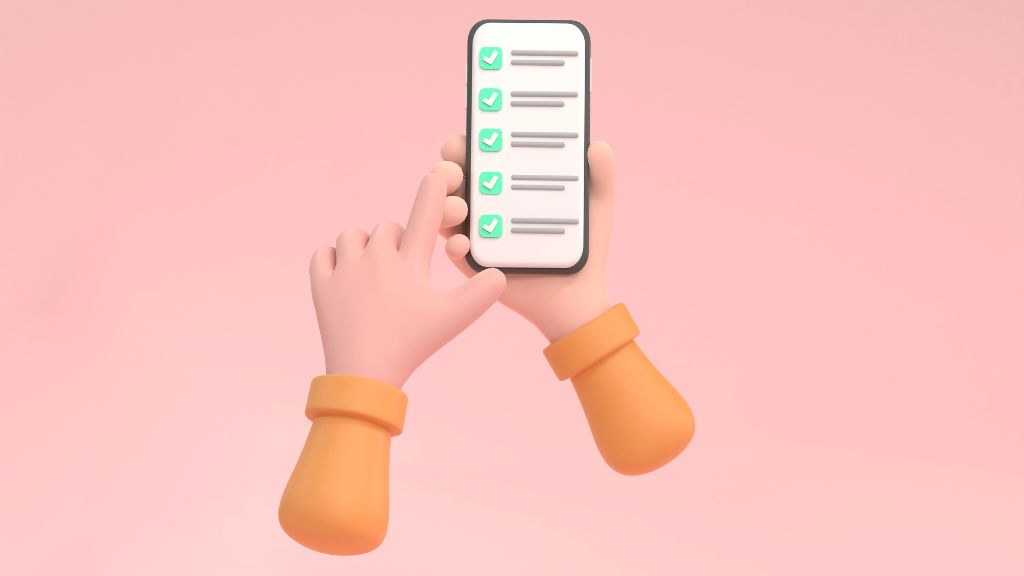
「初診患者の問診に時間がかかり待たせてしまう…」「問診票の判読ミスが多い」など、問診に関する悩みはさまざまです。患者への聞き取りを来院前に行う「事前問診」を行うことで、問診の効率化や精度向上につながります。
ただ、事前問診の具体的な効果がわからず導入を迷う方も多いのではないでしょうか。
本記事では、事前問診がもたらす効果や診療科別のメリットを解説します。業務効率化と患者満足度向上を目指すためのヒントとして、参考にしてみてください。
目次
Webによる事前問診とは?
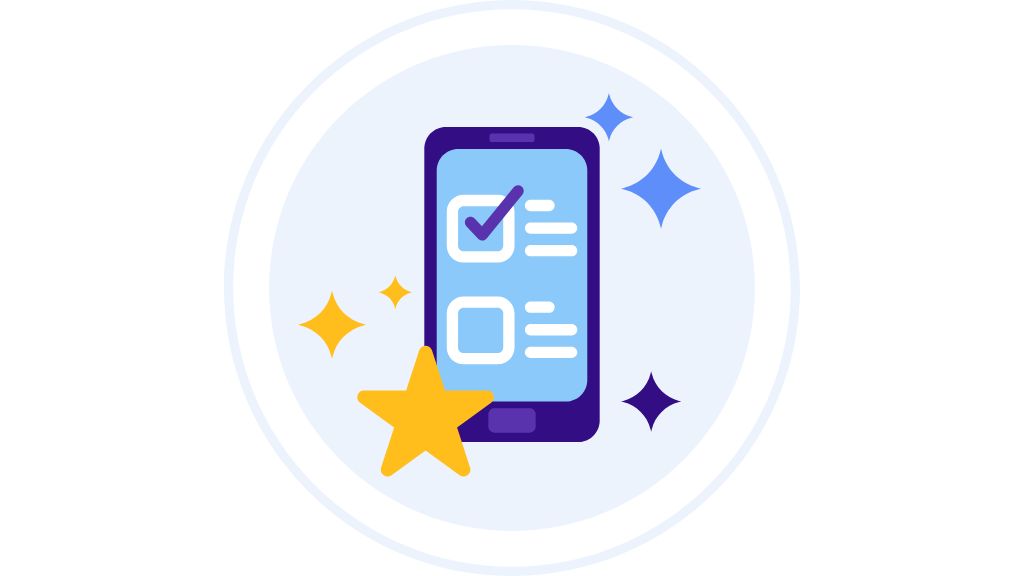
事前問診とは、患者が来院する前に、自身のスマートフォンやパソコンから問診に回答してもらう仕組みです。クリニックのWebサイトや予約確認メールに記載されたリンクから、専用のフォームやアプリにアクセスして回答します。
事前問診はWeb問診システムで行うことが一般的です。紙の問診票と比べて、受付での手渡しや回収、電子カルテへの転記といった一連の手作業が不要になります。データはシステム上で管理されるため、読みにくい文字の判読や転記のミスも起こりません。
また、AIが回答内容に応じて質問を自動生成する「AI問診」と混同されることもありますが、Web問診は、基本的にクリニック側であらかじめ設定した質問に従って進むのが特徴です。問診で得たい情報をコントロールしやすく、効率的な診療を行うことが可能となります。
▼関連記事:
【簡単解説】Web問診とは?メリット・デメリットや選び方を解説
事前問診がもたらす効果

Webによる事前問診を行うことで、具体的にはどのような効果があるのでしょうか。患者とクリニックのメリットにわけて説明します。
| 対象 | メリット | 具体的な内容 |
|---|---|---|
| 患者 | 待ち時間の短縮 |
・来院前に都合の良い場所で問診を済ませられる ・待ち時間の長い初診時の診察効率化になる |
| 回答のしやすさ |
・落ち着いて症状を整理でき、伝え忘れを防げる ・デリケートな内容も回答しやすい ・家族による代理入力も可能 |
|
| クリニック | 業務効率化 |
・問診票の配布、回収、電子カルテへの転記が不要 ・転記ミスや判読の手間がなくなる ・診察時のカルテ入力時間が短縮される |
| 医療の質向上 |
・患者の回答漏れが少なくなる ・診察や検査の準備を効率的に行える ・より精度の高い医療的対応が可能になる |
患者へのメリット│待ち時間短縮・回答しやすくなる
患者へのメリットとしては、待ち時間の短縮や回答のしやすさが挙げられます。
待ち時間が短縮される
Web問診の導入で、患者の待ち時間を短縮できます。来院前に自宅など都合のよい場所で問診を済ませられ、院内で問診票を記入する時間がなくなるためです。
診察待ち時間の不満は、時間のかかる初診でとくに起こりがちです。初診、再診、予約診の3つの待ち時間への満足度を比べた調査では、初診が最も低く統計的な有意差が認められました。患者満足度の向上には、初診時の待ち時間をいかに解消するかが大切といえます。
そのため、初診時に事前問診を行って待ち時間を短縮することは、患者満足度の向上に効果的です。
参考:待ち時間と満足度を組み合わせた外来患者調査│日本医療マネジメント学会雑誌
落ち着いて回答しやすい
患者が自宅で落ち着いて症状を整理しながら入力できる点もメリットです。診察前に慌ててしまい、伝えたいことを記入し忘れることが少なくなります。
また、産婦人科のようにデリケートな内容を扱う診療科では、対面で話しにくい内容でもWeb上なら回答しやすいでしょう。さらに、子どもや高齢者など本人が入力できない場合でも、家族が代理で正確な情報を入力できます。
クリニックのメリット│業務効率化・医療の質向上
事前問診を行うことで、クリニックの業務効率化や医療の質向上につながります。
業務効率化
紙の問診票の配布、回収、電子カルテへの転記作業が不要になり、業務が効率化されます。文字情報として電子カルテに転記されるため、誤字があってもすぐに修正可能です。
また、基本的な症状が電子カルテ上に転記された状態で診察を開始できるため、カルテ入力時間の短縮につながります。SOAPのS欄を患者の話を聞きながら入力する必要なく、やりとりに集中できるでしょう。
問診業務に費やしていた時間が削減され、スタッフが働きやすい環境づくりにつながります。
医療の質向上
事前問診により必要な情報収集ができるため、診療の質向上につながります。Web問診システムは、チャット形式で必須項目を入力しないと次に進めないため、回答漏れが少なく、必要な情報を網羅できます。
また、事前に患者の病歴や服薬情報、希望内容がわかるため、診察前に検査指示をスタッフに出すなど、準備を入念に行うことが可能です。初診時に検査を行い、診察で結果をもとに治療方針を決めることも可能でしょう。
必要な情報を事前に網羅できるため、より精度の高い医療的対応が可能となります。
【診療科別】Web問診で事前問診を行うメリット

Web問診は、診療科の特徴に応じて活用することで患者満足度の向上や業務効率化につながります。小児科、内科、整形外科の3つの診療科を例に、具体的なメリットを紹介します。
1. 小児科
小児科では、子どもが待合室で退屈してしまうケースがあり、事前問診ができると助かる保護者が多いでしょう。また、母親の都合が悪く祖父母が子どもを連れてくる場合でも、母親が事前に回答できるため、情報を正しく把握しやすくなります。
さらに、問診票を特定疾患のスクリーニングに活用することも可能です。例えば、夜尿症であれば「がまん尿量」などの詳しい質問や、子どもの発達に関するスケールを盛り込んでおくと客観的な指標として把握できます。
LINEに慣れた若い世代の保護者にとって、チャット形式で進むWeb問診は抵抗なく受け入れられやすい傾向があります。業務効率を向上させるとともに、保護者から正確な情報を引き出すツールとしてWeb問診は効果的です。
2. 内科
内科は対象とする疾患が幅広く、複数の主訴を持つ患者が多いため、Web問診による詳細な情報収集が役立ちます。
例えば、糖尿病や甲状腺疾患のような生活習慣病では、確認すべき項目が多岐にわたります。Web問診によって、服薬歴やアレルギー、生活習慣など基本情報を事前に把握することが可能です。
また、発熱患者を対象とした問診を設ければ、来院前に感染リスクのある患者を把握し、電話で動線を指示するなど、感染対策にもつなげられます。
幅広い疾患で来院する患者の特徴やリスクを事前に把握することで、診療オペレーションがスムーズになるでしょう。
3. 整形外科
整形外科の診断では、痛みの部位や性質を具体的に把握することが重要です。Web問診では、回答に応じて質問を出しわける分岐機能を活用することで、診断に必要な情報を効率的に集められます。
例えば、「足の症状」と回答した患者にのみ、間歇性跛行(かんけつせいはこう)に関する質問を表示させるといった設定が可能です。
また、けがの患部を撮影して写真をアップロードできる機能もあり、状態を視覚的に理解しやすいでしょう。
さらに、スポーツ外来などより専門的な領域でも有効です。投球回数や練習頻度、アイシングの習慣といった、選手のパフォーマンスに影響する項目を事前に細かく確認できます。診察時に改めて質問する手間を省き、けがの原因究明や具体的な指導に集中できます。
事前問診を導入するデメリットはある?

Web問診にはメリットがある一方、導入時には混乱が生じることもあります。例えば、スマートフォンなどの操作に不慣れな患者は入力方法がわからず、スタッフへの質問が増えることが想定されます。院内にタブレット端末を設置したり、操作をサポートするスタッフを配置したりする対策が必要です。
また、システムの導入には初期費用や月額費用が発生します。さらに、質問項目を増やしすぎるとかえって患者の負担になり、医師が確認する手間も増える可能性があります。
導入後のデメリットや失敗は、患者に寄り添った対策とシステム選びによって防止できます。対策とシステム選びのポイントについては、以下の関連記事も参考にしてみてください。
▼関連記事:
Web問診のデメリットはある?対策と失敗を防ぐシステム選びとは
事前問診の導入なら現役医師開発の「メルプWEB問診」

Webを通じた事前問診は、医療の質向上や業務効率化につながります。待ち時間の短縮にもなり、患者からの満足度も高まります。導入時には混乱を招く可能性もありますが、自院の運営方法や患者特性を加味したシステム選びによって、デメリットを回避することが可能です。
事前問診の導入を検討しているなら、「メルプWEB問診」がおすすめです。現役の医師が開発に携わっており、実際の臨床現場のニーズに基づいた機能が充実しています。
患者がLINEのようなチャット形式で直感的に回答できるため、ITに不慣れな方でも使いやすいのが特徴です。また、メルプ問診百科では診療科ごとに豊富な問診テンプレートを用意しており、簡単に自院独自の問診票を作成できます。
ご相談は無料で承っていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。








